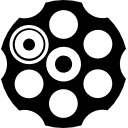空から黒い雨が降り注ぐ午前2時の帰り道。
俺は恋人の雪と電話をしていた。
「だから、明日はモーターショーに行こうぜ」
「うん。じゃあ帰りにケーキ食べて帰ろう?」
「ケーキ?行かねぇよ。行きたきゃ一人で行けよ」
「あ、うん。でも・・・明日は誕」
「ん?煩せぇな!でも何だよ?」
「ううん。ごめんね。・・・行こうねモーターショー。あ、ねぇ」
「なんだよ?」
「・・・好きよ。大好きだからね」
「あ?あぁ、じゃあな」
いつもこんな具合に、俺が決めた場所と時間で
二人は休日を過ごすことが殆んどだった。
雪はいつだって俺の言うことには簡単に従ってきた。
時にそれは、ある種の催眠術やマインドコントール的な
洗脳なのかも知れないとさえ思う程、従順だった。
半年前に知り合った紅葉とは、そっからの腐れ縁で、
今でも、退屈な時に簡単に連絡を取っては、
意味のないセックスを交わした。
そして、それが終わると、
俺は煙草を吸い、紅葉は下着を履いた。
時々、俺の家に置き忘れるピアスや長い髪の毛のせいで、
雪にその手の関係性を知られていたのかも知れなかったが、
雪が何かを言うことはなかったので、俺から何か言うこともなかった。
雪と初めてセックスした時、雪が処女ではないことを知った。
それで、前の彼氏の話を聞いたのだが、それは、
俺以上に酷いもので、暴力や束縛が尋常ではなかったようだった。
その上、その挙句、男に捨てられたそうだ。
雪と知り合ったのはその頃で、俺の女になれよっつったら、
泣きながら「うん」だって。そっから?まぁ、そんなもんだ。
そうして、1年近くが過ぎた。いつも頷くがばりの雪に、
俺は次第と「雪がどこまですれば反抗するのか」を知りたくなった。
ルールはひとつだけ。
「暴力と人格を否定する暴言は吐かない」ということ。
それから半年程だったか。
俺は、雪の作る料理を一口だけ食べて外食に出掛けたり、
帰宅するまで待っていろと、一晩、玄関先で待たせたこともあった。
それでも、雪は「美味しくなかった?ごめんね」
「あ、おかえり」と、微笑んでいた。
俺は、適当に知り合った女を家に連れ込んだ。
「ん?今日は来ねぇよ」
「でも、彼女なんでしょ?」
「馬鹿言え。例えそうでも、花陽の方が良いに決まってるだろ」
「本当に、ダメな男ね」
「煩せぇ。さっさと脱げよ、服」
花陽は知らなかったが、隣の部屋に雪が居ることを俺は知って言った。
そして、泣きながらか、怒り狂ってか、雪が出てくるのを待ったが、
雪は花陽が帰るまで、声を殺してどこかに隠れていた。
俺は、花陽が帰ると勢いよくクローゼットを開けた。
雪は泣きながら笑って「気持ちよかった?」と訊いた。
俺は腹の底からムカついて
「お前さ、俺が死ねって言ったら死ぬのか?」と言った。
雪は「うん。死ぬよ。・・・けど、あなたは言わないわ」と、
涙も拭かずに、自信あり気にそう言い放った。
「あ?何で分かんだよ!そんなこと!この馬鹿女!」
「だって、私が居ないと生きていけないと思うから。寂しすぎて」
「ぶん殴るぞ!貴様この!」
雪は「今まで、暴力を振るわないでいてくれた」と
笑いながら、そして、さらに泣きながら言葉にした。
どこか、俺の思考は止まったように思えた。
瞬間冷凍されたように「ひやり」とした。
「私は汚されてきた。もう生きていけない程に。汚されて・・・」
「昔のことはもう忘れろ。お前はネガティブなんだよ!」
「そして今、私はあなたに綺麗にしてもらっているの」
「なんだよ、それ?」
「あなたは私を愛してくれる?」
「あん?うぜぇな。そうじゃなきゃ、一緒に居ねぇだろ?馬鹿か」
「嬉しい。・・・けど」
「けど、なんだよ?」
「私はあなたを愛したことなんて、一度もないわ」
「何だとテメェ。殺すぞ!」
俺の冷凍は一気に消え去り、ムカつきを通り過ぎ怒りがこみ上げた。
「私はあなたを何度も殺したわ。声を殺して泣きながら、
夢の中で何度も、何度も。今だって、あなたを殺したわ」
「何で、そん時に言わねぇんだよ!この馬鹿がっ!」
「あなたは、本当は優しい人だから」
「うぜぇんだよ!意味分かんねぇよ!」
「優しさは誰かと比べるものじゃない。だからね、だから、
私は、あなたを否定しない。それが、私のルール。だけど、
あなたへの優しさじゃない。私自身への愛情表現。
だから、何にでも頷ける。笑っていられる。
そして、あなたは抱きしめてくれる。
こんな私に何も言わずに抱きしめてくれる。
私はただ抱きしめられて、キスされて、洋服を脱がされて、
触られて、握らされて挿れられる。それが繰り返される。
それで私は満たされているの」
「だから何だよ!ってか、気持ち悪ぃーよ!てめぇ」
「だけど、そんな昨日のコピーのような今日は、
あなたにとって幸せなことではないわ。だって、私は、
ただの一度もあなたを抱きしめたことがないもの。
体だけの関係。それはあなたにとって幸せなことではないわ」
「何だよ、お前、病気か?もういいから今日は帰れ。うぜぇな」
「ううん。帰らない」
「帰れさっさと!俺の言うことが聞けないって言うのかよ!
てめぇ、マジ殺すぞ!」
「それは出来ない。あなたはもう死んでいるから」
「なんだと?」
「ずきり」。頭が痛い。
左のこめかみから頬へと、ぬめっとした体温を感じる。
手を添えると、大量の血液が纏わりついた。
そのまま頭の痛みの感じる部分に手を当てながら振り返ると、
血まみれの雪が金槌を握りしめて立っていた。
痛い。痛いなんてもんじゃない。きっと、頭蓋骨やられたな・・・
目が覚めると、俺は部屋のベッドで寝ていた。
窓の外に見える風景は、満開の桜の木だった。
俺はただ受動的に、それを視界に入れていた。
おそらくは、勝手に入ってきていたのかも知れない。
それほどに自由はなかった。
「夢を誤魔化すのも思い出になるのかもね」
誰かが誰かに言っているようだった。
自分が当事者なのか傍観者なのかの判別も付かない。
俺の視界は少しずつ暗くなり、
しばらくしないうちに、完全な闇と化した。
そして、俺は自分の爪を噛みながら
腐り果てた俺自身を眺めている。
・・・そうして俺は思い出していた。
俺には昔から爪を噛む癖があった。
ガキの頃、義母に相当な暴力を受けた。
親父は、その事実を知らなかった。
もしかしたら見て見ぬ振りだったのかも知れない。
そして、親父が他の女と逃げると、俺は義母に捨てられた。
そして、俺は実母を探した。それが間違いだった。
母は俺を引き取ってくれたが、義父には同じ年の息子が居て、
一流大学へと進学した。今、何をしているかなんて知らないが、
昔から俺は「お荷物」と言われて育った。中三のことだった。
結局、そのまま高校にも行かず、家を出て、
とにかく適当な女とやりまくった。
ゴムなんて付けたことないし、それが、俺の反抗だった。
そして、妊娠させては逃げて逃げまくった。
それは、同意の上での行為であり、罪悪感などではなく、
ただ、親という自信も責任も、全く持てなかったからだった。
そんな時、雪と出会った。俺は誰も見ていないと思って、
爪を噛んでいた所を偶然、雪に見られたことが初対面だった。
「私も噛んじゃうんですよね、爪。・・・一緒ですね」
雪は笑ってそう言った。
俺は雪が運命の人だと感じた。理由などはなかった。
そして、拍子抜けするくらい簡単に付き合うことになり、
俺は雪を大切にしようと心に決めた。
そう決めたはずだったのに・・・。
いつの間に、
あの頃が一番楽しかったなんて思うようになったんだろうか。
俺の人生は、いつだって真っ直ぐな曲線だった。
今はただ、雪に会いたい。会いたい。会いたい。
そして、もしも届くのであれば、こう言いたい。
なぁ、雪。ごめんな。今まで、そんなこと言わせて。
そうだ、デートしよう。遠距離デートだ。
待ち合わせ場所は地球だ。
今すぐ来いよ。
・・・そして今度は、お前が俺を抱きしめてくれないか。
桜は散り、花火も散り、紅葉も枯れゆき、雪が零れ始める。
冬になれば降り注ぐ数多の粉雪。
それでも、二つとして、同じ形の結晶は存在しないもの。
私は雪。他の誰でもない、あなただけの、私だけの雪。
優しく寄り添う紅く染まった2人の寝姿は、まるでジグソーパズルのようだった。
春になっても、私は解けない。
いつになっても、二人は解けない。
きっと、誰にも解けない。